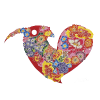
MeiPAM 磯田周佑さん
代表の磯田さんは、もともと東京の大企業にいたが、
あるとき大きな挫折を経験する。
どん底の中で出会った人は、彼の人生を変えた。

働き盛り、34歳の挫折
〜僕には何もなかった〜
横浜出身の磯田周佑さんは、
小豆島への移住を決める37歳まで、
東京の大手通信会社に勤めていた。
会社では事業企画という重要なポジションを任され、
20代半ばにして2年間の海外赴任も経験した。
経済的にも申し分なく、順風満帆なはずだった。
しかし、あることを境に、磯田さんの人生は一変する。
海外赴任から帰国し数年後、33歳になっていた磯田さんは、
社運を賭けた一大プロジェクトを任された。
十数億という規模である。
しかし、彼はこのプロジェクトに勝算を
見出すことができないでいた。
「マーケティング的にも技術的にも
非常に難しいものだったんです」
しかし、大企業が社運を賭けたプロジェクト。
一度転がり出してしまえば、簡単に止めることは
できない。大物タレントの起用もすでに決まっていた。
時期尚早にスタートしたサービスは、
鳴かず飛ばずで失敗に終わる。
結局、磯田さんが責任をとる形で一応の収束となる。
働き盛りであるはずの34歳、すでに疲れ果てていた。
大学を卒業し、新卒で大企業に入社。
大都市・東京で順調に出世街道を歩んでいた
磯田さんだったが、この挫折によってすっかり
働く意味を見失ってしまった。
自らを顧みて、はたと思う。
「気づいたら、僕には何もなかった」
サラリーマンというレールの上にただ乗って、
今まで来てしまった。 もし、今会社を辞めた
としたら、僕には何が残るだろうか……。

社会人大学院での出会い
〜小豆島への予感〜
これまでとは何か違うことを勉強したい、
これまでにない刺激を受けたい。
「会社から逃げたい」という思いもあったかもしれない。
「MBAを取ってみようかな」そう思い立って、
磯田さんは社会人大学院へ通い始める。
毎朝会社へ行き、夜は大学、帰宅後にはレポート作成と、
多忙な日々を送った。土日も大学へ通った。
サラリーマンと学生という二重生活を送るうち、
磯田さんは仕事より大学院生としての生活に刺激を
受けるようになっていた。
同級生と活発な議論を交わしたり、時には授業の後に
飲みに行ったりするようにもなった。
やがて35歳になった磯田さんは、会社で管理職に
なるための試験を受ける。しかし、不合格。
これを機に、さらに磯田さんは会社に
いづらくなっていった。磯田さんの心のバランスは、
次第にくずれていく。
「毎日忙しく仕事に励んでいるのに、
会社ではどうしても輝けない。大学院だけが、
本当の自分として輝ける場所かもしれない……。
そう思い始めました」
とうとう会社に足が向かなくなった磯田さんは、
半年ほど休養することになった。
磯田さんのそんな状況を案じた大学院の同級生が、
ある日彼を飲みに誘ってくれた。その人は
小豆島ヘルシーランドの創業者・柳生好彦さんだった。
柳生さんは、自身が暮らし、会社を起こした小豆島の
おもしろさを磯田さんに話して聞かせた。
社会人大学院には、医者や事業主など、さまざまな
バックボーンの人がいる。柳生さんは、そんな中でも
とりわけ異彩を放っていて、「小豆島から通っているらしい」
「なんだ、あのおっちゃんは!」などと、同級生の間でも
話題になっていたという。
柳生さんと飲みに行った日から、
「東京で働く以外の方法があるのではないだろうか」
そんな考えが磯田さんの頭をよぎり始める。

背中を押した恩師の言葉
〜君は、東京では輝けない〜
“東京以外の場所”を意識し始めた磯田さんは、
「地域活性」や「地域経済」などの、地域を
どうブランディングしていくかをテーマに
した授業を受け始めた。 そんな中で出会った、
今でも恩師と呼ぶ教授が磯田さんに衝撃的な
言葉を突きつける。
「君は、東京じゃ輝けないよ。東京には君の
ような人間なんていっぱいいるんだから」
磯田さんはショックを受けたと同時に
「ああ、確かにそうかもしれない」と思った。
「会社に行っても僕のような奴はいっぱいいる。
皆同じような恰好をして、同じような腕時計をして、
同じような車に乗って、同じような思いで仕事して……
でも結局、経営者によって使い倒される」
教授は、磯田さんにこうも言った。
「君は地域に行きなさい」 さらに、
「君は仕事に対してピュアだし、仕事がしたい
という気持ちも人一倍持っている。でも、東京の
大きな会社の中でのし上がるには、気持ちだけでは
だめだ。君のピュアな熱意は、地域のほうが
伝わりやすいから」と。
磯田さんは、恩師のこの言葉に背中を押され、
柳生さんに「小豆島で働いてみたい」と相談する。
37歳だった。柳生さんは磯田さんの申し出を
受け入れ、自らの会社に招いた。

小豆島の「観光」を考える
〜2年を経て見えた地域の課題〜
38歳になった年、妻とともに小豆島に渡った。
まずは島での生活に馴染み、会社のことを知る
ため幅広く同社の事業に携わった。
地域のために自分はどう貢献できるか。
何をすれば自分の適性が活かせるのか。
今まではそんなこと考えたこともなかったという。
そして見つけたのが、MeiPAMでの活動だった。
MeiPAMは、小豆島の土庄本町にある。
「地域に根ざしたアート活動」をめざし、町内にある
4つのアートスペースを拠点にして、さまざまな企画や
イベントを行っている。
MeiPAMがアートスペースとして使っているのは、
明治時代の呉服屋の蔵をはじめ、空き家となっていた
古い建物。地域が抱えがちな空き家の有効利用にも
一役買っていることになる。
土庄本町は「迷路のまち」と呼ばれる観光地。
中世に瀬戸内海で暴れた海賊が侵入してくるのを阻むため、
あえて町を入り組んだ迷路のように作ったという。
磯田さんはMeiPAMを、迷路のまちへ観光に訪れる人が
立ち寄れる、賑やかな場所にしたいと話す。
小豆島でMeiPAMの活動を始めて約2年。
観光客の中には、小豆島を実際以上に小さな島と
イメージして訪れる人が多いことに気がついた。
目的地まで歩いて行けると思ったら、あまりにも
遠すぎた、じゃあ、といってバス停を案内するが、
1時間に1本しか走っていないことを知り、
愕然とするという。
「行けばなんとかなるだろう、で来てしまうと、
計画通りに観光ができなかったりするんですよね」
そんな人たちを見てきた磯田さんは、ゆくゆくは
「町のコンシェルジュ」のような場を作りたいという。
「観光地としての小豆島には、残念ながらリピーターが
少ないんです。現地で情報がすぐに入手できて、小豆島を
あますところなく楽しめて、また来たいと思ってもらわなければ、
小豆島の観光はよくなっていかない」
“小豆島の旅のキュレーション”として、訪れた人に
観光コースを提案したり、必要とする情報を対面で
提供できる仕組みを考えたい。
2年の活動の中で、そんな目標ができたという。

何を生業として生きるか
〜人生観を変える働き方〜
MeiPAMのほかに、磯田さんは豊島オリヴァルス
という出版事業の代表も務める。豊島で移住生活を
送る編集人・浅野卓夫さんと一緒に、小豆島の
魅力を伝える書籍を作っている。
小豆島をさまざまな切り口で描いた本は、
一冊一冊、装丁にもこだわり丁寧に
作られているのがわかる。
「儲かるほど売れるという本でもないんです。
ただ、どれも良作ばかりなんですよ」と磯田さん。
彼の役割は、編集人の浅野さんが作りたいと思う
本を自由に作れる環境を整えること。そして、
これからもいい本を届けられるよう、経済的な
地盤をしっかり固めること。
以前とはまったく毛色の違う仕事に就く磯田さん。
「あのまま、前の会社にいたら同じことの
繰り返しだったかもしれないし、人間関係も
変わらないまま。今はずっと自由なフィールドに
立たせてもらえていると感じます。
何をやるにも初めての経験。それぞれにしっかり
向き合うことで、経験値もモチベーションも
上がりますよね。その上で、地域に貢献できて
いるという実感があれば、それは“やりがい”に繋がっていく」

小豆島のためにできること
〜若者たちは希望の光〜
地域が抱える人口減少という問題は、
小豆島にもある。島内の高校を出た子ども
たちは、約9割が島外の大学へ進学する。
大学を卒業すれば島へ帰ってくるかというと、そうではない。
今の小豆島の状況をよく知る親たちは、
子どもの将来を憂えてか、自分の代で
畑や家業を終わらせて、子どもには
東京や大阪で働いてもらえばいいと、
どこかで子どもの帰島を諦めている。
大学を卒業した子どもたちは島外で仕事を
見つけ、結婚し、子どもを産み、定住する。
こうして小豆島からは、労働人口が年々減少していく。
「観光事業にだけ力を入れても、その受け皿と
なる働き手がいなければ、残されたおじいちゃん、
おばあちゃんが何百万人もの観光客を相手に
するという状況が生まれてしまう」
と、磯田さんは危惧している。
「例えば島に大学やコミュニティカレッジを作って、
島外から学生に来てもらい、イベントがあれば
地域の人たちと協力してもらえるような、
そんな仕組みづくりができたら島に貢献ができると思うんです」
頭を抱える問題ばかりではない。都会を離れ、
小豆島で暮らしてみて、磯田さんには実感したことがある。
「“コミュニティ”という言葉です」
スタッフが、赤ん坊を仕事場に連れてくる
ことがあるという。会議中に泣き出せば、
その都度中断して皆であやしている。
ある子どもは、場所を選ばずおやつを
食べ始める。磯田さんははじめ、
「なんでプロフェッショナルの現場に
赤ちゃんを連れてくるのだろう」と驚いたという。
しかし、「ここの人たちにとっては不自然でも
なんでもない、ごく普通のことなんですよ」
人口が減少する地域にとって、子どもはとても
大切な存在。そこには、お父さんお母さんだけでなく、
コミュニティが一緒に子育てをしている、
そんな光景があった。地域の希望となる子どもを
皆で育てるのは、考えてみれば人間のあたりまえの
行為なのかもしれない。
「この子が10歳、15歳になったとき、果たして
小豆島は存在しているのだろうか。そんなことを
考えると、自分たちが今頑張らなければと、
自然に思えるんです。たとえその子が自分の子じゃなくても」
磯田さん自身、いずれは子どもがほしいと話す。
「コミュニティの素晴らしさを身近に感じている
からこそ、僕もきっと安心して小豆島で子育てができる」
そういって目を輝かせた。 大きな会社で経験した大きな
挫折、それが引き金となって通い始めた大学院。
何もかもに嫌気がさしたころ、小豆島の人と出会い、
教授の「地域へ行け」という言葉に動かされ、
38歳にして小豆島へ移住するという大きな決断をした。
そして今、のびのびと島に暮らし、地域のために生き生きと働いている。
東京にいたままじゃ、輝けなかった人生。
それが今、こんなに輝いて見えるのだから、
人生は本当にわからない。




