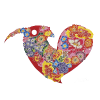
オリーブ染め工房「木の花」高木加奈子さん
生きていくということ
緑色をしたその果実で糸を染めるとき、
鮮やかな「島色」を生み出す。
それはまるで、小豆島の自然を映し取ったような―。

故郷に生き、故郷を愛する
微笑むようなオリーブの色
彼女の紡ぎ出す鮮やかな色は、優しくて穏やか。
どこか微笑んでいるようにすら感じるその色は、
都会の真ん中にいては見ることができない。
オリーブ染め工房を営む高木加奈子さん。
美しい故郷の島を慈しみながら、
この土地だけの色を丁寧に、丁寧に。
故郷の自然を愛しながら生きることを選んだ彼女は、
私たちに大切なことを教えてくれた。

あの頃があったから
最初から最後まで自分の手で
今は小豆島で工房を営む高木さんだが、
年前までは島を離れていた。
高校卒業と共に島を離れ、大学卒業、就職、結婚…と、
人生の節目は島の外で迎えた。
仕事はアパレル関係だった。
自分でパターンを起こし、デザイン、縫製と、
何から何までこなす日々。
最初から最後まで、全ての工程を自分の手でやった。
「この工房を持った今は、糸を染めるところから
作品にするところまで、 すべて自分でやっています。
あの頃の経験が役に立っているんでしょうね」
故郷を離れて積んだ経験は、今に活かされている。

ふるさとの色にみちびかれ
島を出たから見えたもの
島を離れ、来る日も来る日も衣料製品に
触れて過ごしたアパレル時代。
高木さんは徐々に、化学染料での染色に
違和感を抱くようになった。
もっと安心な方法を、と考えてたどり着いたのが、
草木染めだった。
自然の花々や草木が内に秘める色たちが、
思いがけない形で現れる草木染め。
「小豆島のオリーブで染めたらどんな色になるんだろう」
思い入れのある、故郷の素材で染めてみたら
きっといい色が出るに違いない。
期待は膨らんだ。兄の知り合いから
分けてもらったオリーブを使って、
さっそく染めてみた。
「できあがったその色が、私にとっては
故郷の穏やかさ、そのままのような色だったんです」
そんな素敵な色を、ふるさとのオリーブで
表現することができる。
ふるさとに帰らない理由は見当たらなかった。

すべての色をオリーブから
オリーブがくれる島の色
島のあたたかな日差しと大地に育まれたオリーブは、
優しくて穏やかなカーキの色を出す。
でも、高木さんがつくるストールや手鞠などの作品には、
カーキ色だけではなく、たくさんの色の糸が使われている。
それら全てに必ずオリーブ染めを施してある。
「黄色は島の春を告げる色。
これは島の秋の穏やかな小春日和。
こっちは実の熟したオリーブの色。
青は島の空と海、赤は寒霞渓の紅葉。
すべて小豆島のオリーブで染めています。
オリーブのつくり出す色から島の様子が
見えるみたいで、不思議でしょ」
”島色”と呼ぶ鮮やかな色で人々を魅了する彼女こそ、
誰よりもオリーブの持つ限りない色に魅せられている。

オリーブから色を頂いて生きている
一枚の葉も余すことなく
そんな彼女の工房でひときわ目を引くのが、
オリーブで染めた糸をふんだんに使った“島てまり”。
たくさんの”島色”が細かい模様となって散りばめられている、
目にも楽しい作品である。
カラフルでありながらまとまりのある優しい色が
織り成す模様たち。その表面の美しさに目を
奪われてしまうが、実は土台になる球体の部分にも
オリーブが隠れている。
染色に使った後のオリーブの葉を、
チップにして詰め込んであるのだ。
「私はオリーブから色をもらって生きてるから。
ほんの少しでも無駄にすることはできないんです」
そこに垣間見えるこだわりに、
オリーブ染めへの愛をひしひしと感じる。

若い人が帰ってくる島に
帰ってきた私にできること
ふるさとで大好きなことを見つけた高木さん。
彼女には、少し気がかりなことがある。
今でこそ彼女の工房の中には、
外を元気に走っていく子供たちの声が響いてくるが、
小豆島に暮らす若者の数は決して多いとはいえない。
島の未来の担い手の数は、確実に減っている。
小豆島のような、島内に大学がなく、
働き口の選択肢も少ない地域では、
進学や就職を機に若者の多くがふるさとを後にする。
高木さんのように、やっぱり小豆島が好きで
戻ってくる人もいる。
けれど、そのまま島外での生活を選ぶ人も多い。
「帰ってきてもらうためには、生活が確保できること、
それが大事だと思っています。きれいな海や山、
空気も魅力だけど、それだけでは生きていけませんからね」
だからこそ、島を出た若い人たちが、
島の生活に可能性を感じてくれるような、
そんな産業を少しでも増やしていくことが、
島に帰ってきた自分にできることではないか。
そう彼女は語る。

故郷を愛し、生きていくということ
島を誇りに生きて欲しい
7年前、ふるさとに再び暮らすようになって
驚いたことがあった。 島の人達の中に、
田舎者と思われるのを気にしてか、
ふるさとのことを話したがらない人たちがいたのだ。
それ以来、島の外に出るときには必ずオリーブ染めの
ものを身に付け、小豆島の魅力をアピールするようにしている。
「島の人たちには、小豆島に生まれたことを
誇りに思って生きて欲しいんです」
たまたま自分を魅了したのが、故郷のオリーブの色だった。
大切なふるさとを映すかのようなその色が、
高木さんは大好きでたまらない。
彼女が故郷に戻ってきたのも、
小豆島で生まれたことに誇りを持てるのも、
すべてオリーブのおかげ。
いたってシンプルなのである。
離れてはみたけれど、やっぱり故郷のものがいい、
ふるさとが好き。そんな純粋な心こそ、人を故郷に呼び戻す。
島を支える産業だって、そんな気持ちなくしては生まれない。
もう一度、故郷を見つめてみよう。
小豆島にオリーブの素敵な色があるように、
私たちそれぞれの故郷にもきっと宝物があるはずだ。
高木さんの笑顔はそう思わせてくれる。




