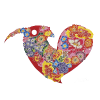
「山田オリーブ園」山田典章さん
山田典章さんの物語り
オリーブの有機栽培を成功させたひとりの男がいる
努力は必ず実る―、挑む者に勇気をくれる物語り

新風 からり島に吹き
「山田オリーブ園」の物語り
穏やかな瀬戸の内海(うちうみ)に浮かぶ、小豆島。
海は凪(な)ぎ、からり、やさしく陽は照って、
その中で、健やかに枝葉を伸ばす、樹々がある。
緑の樹影(こかげ)、オリーブたち。
この地中海ゆかりの、古い歴史を持つ果樹は、
日本の瀬戸内の海に、自分たちの“ふるさと”を見て―、
そうして、今からおよそ100年前、
小豆島の地に、力強く、その根を下ろした。
先人たちは、100年もの間、島と語り、オリーブと生き、
そうして、今また、この樹の、次の100年の、
新しい扉を開く、緑の新風が、颯(さつ)と吹き―、
自然のままに、生(き)のままに、
「山田オリーブ園」の物語り。

慈しみの一念
小豆島オリーブの100年
オリーブと小豆島の出逢いは、
日露戦争後の、1908(明治41)年にまで遡(さかのぼ)る。
ロシアに勝利し、漁業権を拡大させた日本は、
遠洋漁業に必要な、魚介の保存油を、切に求めていた。
実より良質な油が採れるオリーブの栽培は、
当時の日本にとって、「国策」とも言うべきものだった。
その中で、明治政府によって、小豆島に連れてこられた、
外国生まれの、ちいさなオリーブの苗木たち。
栽培に関する、技術や知識を持たない先人たちは、
ただただ、慈しみの一念で、育て上げ―、
そうして、1910(明治43)年に、初めて実を結び、
以来、小豆島は、日本におけるオリーブ栽培の楽園として、
100年間、その恵みの果実を、産し続けている。

小豆島は、ちかく
思い出と縁に導かれ
その小豆島オリーブ100年の歴史に、
新しい風を吹き入れる、ひとりのオリーブ農家がいる。
「山田オリーブ園」園主・山田典章(のりあき)さん。
山田さんと、この瀬戸内の島との縁(えにし)は、
岡山で農業を学んでいた、大学時代より始まった。
大学の夏休みに、小豆島の近くに浮かぶ直島で、
体験キャンプのアルバイトをした経験が、
瀬戸内の島の魅力に触れた、さいしょ。
大学卒業後、20年間、東京の地で勤めてきたが、
ときどき、島の思い出が、ふわり、心をつついた。
奥さんが小豆島出身という奇縁も、背中を押し、
自然と、小豆島が身近なものになっていた。
そうして2010年、小豆島への移住を、決めた。

調査、推論そして実践
ゾウムシくんの好き 嫌い
山田さんは、小豆島の地で、農業をやろうと思った。
どうせやるなら、有機をやろうと、決めた。
しかし、当時、オリーブの有機栽培など、
到底、不可能だというのが、島での定説だった。
それは、樹を齧る困り者・ゾウムシがいるから―。
しかし、山田さんは、淡々と、考える。
じゃあ、そのゾウムシを、何とかすればいいわけだ。
山田さんは、文献を調べ、島中のゾウムシを採集し、
ゾウムシの「好き、嫌い」を、洗い出した。
農薬を使って、ゾウムシを追い出すのではなく、
元々、彼らの好まない環境の畑を作ればいい。
あとは、地道に、剪定、草取り、そして、見回り―。
やるべきを淡々とこなし、無農薬でもゾウムシは半減。
こうして、国内初の有機JAS認定オリーブ農園が、誕生した。

常識は変わっていい
販路の開拓も、柔軟に
これまで、小豆島では、オリーブは、
塩漬けなどに加工して出荷するのが、常識だった。
山田さんも、最初はそれに倣(なら)っていた。
しかし、東京のレストランの、本場仕込みのシェフに、
思いもよらない、ひと言をもらった。
―余計なことはしてくれるな。
そう、本場のシェフから言わせれば、
料理に合わせて、生の実から加工するのは、
他の誰でもない、シェフ自身の仕事だということ。
「山田オリーブ園」の出荷先は、大半が首都圏で、
そこには、生の実を求める、個人のお客さんまでいる。
そんなお客さんは、加工作業それ自体を、楽しむ。
山田さんは、その都会のニーズを敏感に掴み、
新たな販路を築いて―、そう、常識は変わっていい。

たんたんと、自然体
オリーブのあしたを描く
山田さんには、妙な気負いというものが、ない。
「移住」という、人生の大きな選択に際しても、
自然の流れ、まにまに、肩肘張らず、
いつの間にか、からりと、島に馴染んでいる。
これは、小豆島が本質的に持つ、
自由さ、鷹揚(おうよう)さも、手伝っているのかもしれない。
その島の闊達(かったつ)な雰囲気の中で、
毎日、オリーブの樹々と向き合っていると、
いつしか、その一本一本に、瑞々(みずみず)しい個性を見て―。
自分よりも長く、そう、1000年すらも生き抜く、
オリーブの樹に、眩しい「いのち」を感じながら、
山田さんは、淡々と、しかし、慈しみ深く、
次の100年を描く、小豆島のオリーブを、育てていく。




