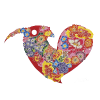
「本家長門屋」鈴木素子おかみ
笑顔と共に、「今」に感謝し、「今」に生きる―
会津老舗和菓子屋が贈る、生きることへのメッセージ

「おわいなはんしょ!」
「本家長門屋」鈴木素子おかみの物語り
鶴ヶ城の西方、湯川に近い城下街の一角に、
張りのある会津弁が響き、
明るい笑い声が溢れるお菓子屋がある。
会津駄菓子「本家長門屋」。
会津の伝統的な「駄菓子」を扱う、
この由緒正しい老舗和菓子屋の店内では、
冗談を繰り出しては、闊達(かったつ)に笑うおかみさんと、
その母を優しくサポートする娘さんの名コンビが、
お客を晴れ晴れしく迎えてくれる。
作り物ではない、本物の笑顔の清々しさ。
そして、その拠って立つ、生活人としての哲学。
会津の「駄菓子」を通じて、
今に生きる全国の人たちに、大切なことを伝えてくれる―、
「本家長門屋」鈴木素子おかみの物語り。

会津駄菓子と共に
長門屋160年の歴史
嘉永元(1848)年、
時の藩主・松平容敬(かたたか)公から、
「庶民の菓子を作れ」との命を受けたのが、
長門屋のはじまり。
そして、嘉永5(1852)年には、
早くも、会津の名店・名所番付表である、
「会津五副対」にも掲載されている。
伝統菓子、郷土菓子を扱う長門屋が、
自ら「駄菓子」と銘打つ理由も、この歴史にある。
江戸時代の「駄菓子」とは、
貴重な白砂糖を使った献上用の「上菓子」に対し、
黒砂糖、ひえ、あわ、豆など、
庶民的な材料で作った、素朴な菓子のことだった。
このように、
「駄菓子」を本来の意味で使うことによって、
創業のきっかけとなった、会津の殿様への敬意と、
江戸時代の昔から、庶民に親しまれてきたという誇り―、
そのふたつを、明確に示しているのだ。

伝統を守る長門屋の味
一つひとつ、丁寧に手作り
江戸時代の味を今に伝える、
「黒ぱん」「おこし」に、「とり飴」。
「あんこ玉」などの定番駄菓子も、多種多様。
店頭には、そんなお菓子たちが、
色とりどりに、ずらりと並ぶ。
実はこれらのほとんどが、
昔ながらの製法で手作りされている。
たとえば、飴ひとつ取っても、
鉈と木槌を使って切り出す熟練の技や、
凧糸を使って丸みを帯びた切り口を作る技など、
昔から伝わる技術は、数多く存在している。
そんな数々の技術を習得した会津の職人が、
一つひとつ想いを込めて丁寧に作り上げる、
会津の伝統的なお菓子。
それが、長門屋の「駄菓子」なのだ。

苦衷の中で、起こった変化
震災―、一時はもうだめかと
嫁に来て以来、
素子おかみは仕事を生活の中心に据え、
長門屋と共に生きてきた。
しかし、平成23(2011)年、
あの東日本大震災が起こった。
最初の半年は、本当に苦しかった。
客足はめっきり減って、
3、40年ずっと来てくれていた修学旅行生も、
ゼロになった。
―この商売、ここで終わっちゃうのかな。
そんなことすら、頭をよぎった。
けれども、その後、
落ち着きを取り戻すと共に、徐々に客足が戻り、
中には、遠方からわざわざ、
足を運んでくれる人たちも増えてきた。
そんなお客さんたちと接していく中で、
おかみの心の中に、「ある変化」が起こった。

「長門屋」を架け橋に
会津でお菓子をつくる意味
遠くにあって、
会津を想ってくれる人びとの存在。
震災を通してそれに気付けたことで、
この地で会津駄菓子を作り続けることの意味が、
はっきりと立ち現われてきた。
会津を故郷として、懐かしんでくれる人たち、
会津に憧憬や共感を寄せてくれる人たち。
様々なかたちで、会津を思ってくれる人びとに、
「会津、なおここにあり」という気概を、
お菓子を通じて伝えたい。
この「長門屋」を、
会津の地への想いを繋ぐ、架け橋にしたい。
今、素子おかみは、感謝と共に、
その想いを、たいせつに抱いている。

シンプルに楽しく、「今」を生きる
会津発、「生活人」のメッセージ
震災で気付いたもうひとつのことは、
人生は一度きり、という単純な事実。
雑多な固定観念に縛られて、
義務的にあくせく働くのでは、つまらない。
「今」を楽しみながら、「今」を生きる。
肩の力を抜いて、自然体で仕事をし、
目の前のお客さんと、心から楽みながらおしゃべり。
そうして、人と、あたたかく繋がっていく。
そう、それだけでいい。
そう思ったら、毎日が本当に幸せになった。
素子おかみはそう言って、
娘さんと気持ちよく笑い合う。
震災後の苦しみに呑まれることなく、
自然体で、笑顔を絶やさずに生きる鈴木さん一家。
その姿は期せずして、
「今」を生き惑うすべての人たちへの、
心に沁みるメッセージになっている。




