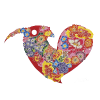
赤穂屋太鼓座 長田洋さん
長田さんは、赤穂屋地区の団長として祭りの大舞台に臨む。
彼が思う祭りとは、そして小豆島の現状とは。

秋の小豆島の風物詩
八幡神社の太鼓祭り
「あの、左側の棒の先頭にいるのは、どこの子?」
「あれはね、森下さんちの、次男坊だよ」
「そう、立派になったんだねぇ」
「それじゃぁ、あの太鼓台の上に乗ってる子どもは誰?」
「ほら、角の床屋さんとこの孫だよ。今、小学校に通っている」
沿道で太鼓台のほうを見ながら、
年配の女性が話しているのが聞こえてくる。
毎年10月、小豆島で行われる秋祭り太鼓台奉納。
小豆島の秋の風物詩である。
土庄町渕崎で行われる「富丘八幡神社祭り」も、その一つ。
これから、その宵祭りが行われるという。
男衆が飾り付けられた太鼓台をかつぎ、
子どもが太鼓台の周りをついて歩く。
地区の人たちが総出で参加する祭り。
「太鼓祭りは、町内みんなが参加しますからね。
顔を覚えてもらうのに良い機会なんですよ」
赤穂屋太鼓座の団長、長田洋さんは、そう教えてくれた。
「ご近所の繋がりって、年々希薄になってきているでしょ。
コミュニティがなくなってきている。
それは都市だけでなく、田舎も同じなんです」
若い人たちが島外に出て行き、年配者だけが残る。
少子高齢化という波が、ここ小豆島にも訪れていた。

幼き日の「祭り」の記憶
海峡に映る、ぼんぼりの灯り
今の若者たちと同じように、長田さんも一度、小豆島を離れた。
けれど、祭りとなれば皆で一緒に盛り上がって楽しめる。
そんな感覚があって、毎年祭りの時期には島に帰ってきたという。
「子どもの頃に見た宵祭りがね、何とも言えなくて。
全部の町の太鼓台が提灯をつけて、土渕海峡付近に集まるんです。
そうすると、海峡の水面に提灯の灯りが映って、
それはもう……言葉にできないほど幻想的で綺麗だった」
太鼓祭り前日には、提灯で飾り付けた太鼓台が町内を練り歩く、
通称「ぼんぼり祭り」という宵祭りが開催される。
ぼんぼりをつけた太鼓台についていくと、子どもたちは飴や飲み物をもらえた。
仲間たちとワイワイ騒ぎつつ、お菓子を食べながら太鼓台について地域を練り歩く。
「手を出せば、飴玉を貰えるというのが祭りについての最初の印象ですね。
その日だけは、どんなに夜遅くまで遊んでいても、大人に怒られない」
長田さんは、子どもの頃のぼんぼり祭りが忘れられないと言う。
楽しくて、楽しくて、子どもも大人も時間を忘れて、
騒ぎ、遊び、飲み、語り合った。

人口減少と、衰退していく祭り
思い出で終わらせたくない
毎年、華やかに行われていた「ぼんぼり祭り」。
けれど、人口が減っていくにつれ、一つ二つと
ぼんぼり祭りに参加できない地区が出始める。
毎年、次々と不参加の町内が現れ、宵祭りはついになくなってしまった。
「小豆島に帰ってきたときにね、『あれ、祭りってこんなだった?』
っていう違和感があったんですよ。昔はもっと、盛り上がっていたよねって」
地域が一斉に集まって行う宵祭りはなくなったものの、
各地区それぞれの形で宵祭りは継続されていた。
けれど、長田さんの記憶にある形とは違っていた。
心躍る、賑やかで華やかなものではない。
そこで、赤穂屋の隣の地区に、
一緒に時間を合わせて宵祭りをしようという話を持ちかけた。
「一緒に昔の宵祭りを作ろう。昔のままとはいかないまでも、
昔に近い形のものを一緒に作ろうよ、と話しました」
一度やめてしまったものを動かすには大きなエネルギーが要る。
もう一度、昔の形に戻すという話を持ち掛けたとき、
すんなりと物事は運ばなかった。

地区の誇り、赤穂屋の法被
袖を通すまで〜心の葛藤
人口減少により、太鼓台の担ぎ手である
「舁き(かき)手」が募れない地区もあったという。
そんな状況の中、祭りを継続するために奮闘したのが青年団の人たちだった。
祭りの準備、運営、後片付けまで、裏方の準備を少ない人数が協力して行う。
そのとき、青年団が着ていた法被(はっぴ)を見て、長田さんはハッとした。
「色が違う……」
祭りでは、地区ごとにそれぞれおそろいの法被がある。
法被の色や柄を見れば、どこの地区の人か一目瞭然で、
祭りを担う人たちの誇りであり、団結の証でもあった。
「同じ地区内なのに、青年団の法被だけが違っていたんですよ。
それでね、最初は違和感があった」
しかし、そこには意味があることに気付かされる。
「青年団の法被を着た人たちが、
一生懸命頑張っているのがよく見えるわけですよ」
祭りで賑わう中、皆と違う法被を着た青年団の人たちが、
汗だくになりながら動き回っている。
舁き手だけではなく、子どもたちや見物人たちに声をかけ、
一丸となって祭りを盛り上げていた。
島に帰ってきて青年団に入った長田さんは、
祭りを見る側から動かす側になった。
青年団の一員として、それから赤穂屋の団長として、
地区のため中心に立って祭りを盛り上げようと意気込む。
その役割の重みを知り、今では誇りを持って青年団の法被を着るという。

島を離れた人にも
「お帰りなさい」と笑顔で言いたい
ちょっとしたことでも一生懸命、頑張って働く。
青年団の活動は人の心を動かし、今では若い人に「一緒にやろう」と声をかけると、
みんな喜んで協力してくれるようになった。
「法被のおかげでね」
長田さんは笑って言う。
あのハッピを着たい、青年団に入って活躍したい、
そんな若手の声が耳に入ってくる。
賛否はあるけれど、祭りや青年団の活動は
残していかなければいけないものだと、長田さんは言う。
「祭りが受け皿となり、島に帰ってきた人たちが
集まれる場所になったら良いと思うんです」
島外に出てしまうと、もう一度中に入るのは難しい風潮がある。
これは小豆島だけではなく、どの地域も同じ。
自分たちを覚えていてくれるだろうか、受け入れてもらえるのだろうか、
そんな不安を誰もが抱く。
彼らに「お帰りなさい」と言って皆をまとめることができる、
そんな青年団を作っていきたい。
「だからこそ、ぼんぼり祭りや太鼓祭りは大事」
皆が集まり、顔を覚えてもらう。
祭りは神様に感謝をするだけではなく、
地域の人たちの絆を深める交流の場でもあるのだ。

伝統を守り、今も受け入れる
島外から力を借りる新しい試み
宵祭りの復活の波が広がれば、
長田さんたちが子どもの頃に見たような、
華やかなぼんぼり祭りをもう一度見られるかもしれない。
けれど、まだまだ問題は山積みだ。
「舁き手や乗り手がいなくて、
本祭りに太鼓台が出せない地区もあるんです」
要鉄(ようてつ)地区では、江戸時代後期から、
船の形をしただんじりに子どもを乗せて日本舞踊を奉納してきた。
しかし、少子化に伴い踊りを習う子どもがいなくなり、
だんじりを出さないという話が持ち上がった。
地区内で協議した結果、なんと引き手とパフォーマーを
「募集する」という新たな試みがスタートした。
「島ですから、閉鎖的な部分は少なからずあると思うんです。
でも、様々なことをやっていかないと祭りの継続は難しい」
10月に小豆島を訪れたら、どこに行っても祭りが見られる。
それが秋の小豆島らしい風景であり、小豆島の良さでもある。
今ここで、祭りを盛り上げていかなければ、
小豆島自体が衰退してしまう。
だからこそ、無理をしてでもぼんぼり祭りを復活させた。
無理をするのは無駄ではなく、無理は糧となり花が開く。
その花は実を結び、次々と咲いていくはずだ。
長田さんをはじめ、富丘八幡神社の祭りを担う団長たちは思う。
自分たちが子どものときに感じたように、
新しい世代にも「お祭りは楽しいもの」と受け止めてほしい。
そして大人になり、その楽しさを次の世代にも伝えてほしいと。
「そのとき、僕らが一歩引いた目線で祭りを見ることができたら良いですね。
のんびり酒でも飲みながら、脇でワーワー言う感じね」
そういって長田さんは明るく笑った。




