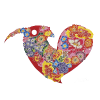
会津漆器 工房鈴蘭 鈴木あゆみさん
会津に伝わる伝統工芸を現代風にアレンジ
この素晴らしい文化を、もっと知ってほしいから

現代に伝統を生かす
会津漆器、という言葉がある。 言葉には印象がつきまとう。
例えばそれは隙のない曲線美。 あるいは抑制の利いた華々しい蒔絵。
不浄を寄せ付けぬ気高い赤。 この世の深淵を見つめているような、黒。
印象はときに先入観を生む。 先入観はやがてその印象を補強する。
七日町通りに桃色の暖簾がかかっている。 飾り気のない薄墨で書かれた
「鈴蘭」の文字。 るい店内に並べられている品々には、
そういう印象の中の「会津漆器」とは離れた物が多い。
例えば適度に粗さがあってよく馴染む手触り。 円を基調にした
簡素で親しみやすい模様。 ほのかな温かさを覚えるような、臙脂や薄桃色。
中にはガラスを漆塗りしたものまで。
会津漆器、という伝統がある。 その伝統を見つめ直す、
工房鈴蘭の物語り。

身近な漆器へ
工房鈴蘭のコンセプトは「かわいい漆器」なのだと、
店を切り盛りする鈴木あゆみさんは笑顔で教えてくれる。
使うと傷が付くのではないか? すぐ変色してしまうのでは?
人々の日常生活から、漆器という存在が遠ざかって久しい。
ゆえに先入観ばかりが残り、漆器は更に敬遠される。
でもきっとむやみやたらに高いのだろう。
そうだ、食器棚の中に飾っておこう。
願わくは漆器の敷居をさげて、もっと身近なものに。
そのためにも、まずは「塗り物」に興味を持ってほしい。
だから、工房鈴蘭で扱っている品々は 必ずしも狭い意味での「漆器」に限らない。
例えば漆の代わりに元が透明なウレタンを使った器。
同じ技術を使っても、漆より自由な色彩で塗ることができる。
他にもガラスを素地にして、ラメを混ぜつつ漆塗りしたものも。
木地と漆の組み合わせでは出せない風合いがあれば、
その良さを生かしていく工夫を、積極的に追い求めていく。

会津の魅力、伝統の魅力
あゆみさんは、初めから漆器の道を志していたわけではない。
学生時代はソフトボールに打ち込み、 やがて実業団のチームに入る。
それが不況の煽りで入社二年後に廃部となり、目標を見失った。
自分のやりたいことを、もう一度探してみる。業務の傍らで、
大学の通信制課程に籍を置く日々が始まった。
登校日には他県出身の人とも顔を合わせる。その折々に、会津はいいね、
と、あゆみさんは言われたのだった。
お酒はおいしいし、お米もおいしいし、自然が、歴史が、伝統工芸があると。
ただ正直、それの何が魅力的なのか、最初はよく分からなかった。
分からないなりに、何か魅力があるのだろうと思いつつ、
これから会津で生きていくということを、初めて意識した。
会津にいるんだったら、何をしよう?
父が会津漆器の塗師だったことに、ふと思い至った。

会津漆器の未来のために
あゆみさんは、子どもの頃からものづくりが好きで、
父の邦治さんの職場にも、毎週のように出入りしていた。
そうして今、成長して父から改めて聞く会津漆器の未来は
決して明るいものではなかった。
会津漆器の生産では、 現在でも分業制と問屋制が機能している。
各工程を受け持つ職人と商人は原則として分離していて、
それぞれの間は昔から続く問屋によって取り持たれている。
問屋は職人の面倒を見て、職人に仕事をおろしてくれる。
しかし長く続く不況の中で、仕事の数自体が減ってしまった。
高級な一品物は無論、量産品も価格で海外の物には敵わない。
己の技で食べてきた、職人らの苦衷はいかばかりだろう。
この技術がなくなってしまうのはもったいない。
会津の魅力、その内のひとつが、このままでは絶えてしまう。
一年近く悩んだ末に、あゆみさんは結論を出した。

そうだ、作って売ろう
会津漆器技術後継者訓練校。
あゆみさんは会社を辞め、 この学校で二年間、漆塗りを学んだ。
やはり会津漆器の伝統を想う同期の学生たちに囲まれながら、
父とともに、工房鈴蘭でやっていく決意を固めた。
工房鈴蘭は邦治さんが独立して開いた工房で、
市街地を東に離れた静かな山の中に建物を構えている。
木に囲まれていて湿度も安定し、夏にも暑くなりすぎない。
流れる空気も街中に比べて埃が少なく、塗りに適した環境だった。
問屋の仕事が減っていく中、邦治さんは考えていた。
そろそろ自分で、今まで見たこともないようなものを作りたい。
漆を取り入れたもので、全く新しい何かを、と。
一方で娘のあゆみさんも、会津漆器の将来を考え続けていた。
職人が生き残り、会津で仕事を続けていくにはどうするか。
―それならば、作って売ろう。
二人の辿り着いた答えが、それだった。

普段の生活に、漆器を
最初の数年は様々な展示会に参加するところから始めた。
評価は必ずしも芳しくなく、試行錯誤の日々が続いた。
木製の新製品だけでは行き詰る。 はっきりとそう思ったのは、
まさにその頃だった。 今の生活では、味噌汁を毎日飲むということもない。
では、ガラスならどうだろう?
ガラスならお水でもお茶でもお酒でも、普段からよく使う。
しかし、ガラスは表面が滑らかで、漆とは決定的に相性が悪い。
邦治さんは何度も創意工夫を積み重ねた。
苦労の末に完成した、「漆塗りのガラス」という逸品。
展示会での反応が、変わった。
これなら行ける。 二人の間に確信が生まれた。
そうして七日町の大通りに、桃色の暖簾が翻った。
職人である塗師が、自ら構えた店。
工房鈴蘭の直売店が、いよいよ動き始めた。

使われる漆器へ
直売店を開設してから気付いたことも多い。 商品を出すと、
すぐにお客さんの「声」が返ってくる。
―例えば、漆器の色が暗いという「声」。
開店当初は赤や黒、昔ながらの色ばかりが並んでいた。
こちらを黒で塗ったなら、こちらは赤で塗る。
伝統と共に根を張っていた、ある種の固定観念。
こういう色も出せるのか、出していいのか。
試しに明るい色を使ってみて、作っている側が驚かされた。
―他にも、漆器は傷付きやすくて怖いという「声」。
確かに木地や漆の特性上、漆器の手入れには幾つかの制約が付く。
それが必要以上に強調されて、敬遠される原因のひとつになっていた。
実際に傷が付きにくく、しかも、そう思える塗りはないだろうか。
工房鈴蘭の特徴でもある、適度に粗い手触りの塗りは、
そんな細やかな心遣いから生まれたものだった。

鈴蘭の立ち位置
伝統工芸とは、なんだろう? 伝統を守るとは、どういうことなのだろう?
あゆみさんは、常にそう自問し続けてきた。
会津漆器だって、最初からずっとこの形だったわけではない。
何百年も昔から、道具を変えながら、素材を変えながら―。
その時代に必要なものとして、 脈々と生かされてきて、今に至る。
守り続けなければいけないことは、確かにある。
様々な先人たちが継いできた、会津漆器という伝統。
自分たちは、その積み上げられてきた価値の上に立たせてもらい、
そして、その価値を次代に繋げていくお役目をいただいている。
一方で、徒に変化を拒んでもいけない。
時代に合わせて、人々と共に変わっていかないと、
最早それは、必要とされるものではなくなってしまうはずだ。
変わってもいい。自由にやってもいい。
それがむしろ、伝統を守るということに繋がるのかもしれない。
自分たちの取れる立ち位置は、きっとそこなのだ。
工房鈴蘭では、時代の新しい風を掴もうとする親子二人、
今日もひとつずつ心を込めて、「身近な漆器」を作り続けている。




