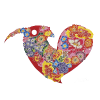
お手火神事 お手火奉製作業
火祭りに懸けるそれぞれの想いは、
私たちの心にも熱い火を点ける

随身門の前の、巨大な松明
細雨煙る沼名前の参道に集まる人びと
7月の頭の、朝。しとしとと糠雨(ぬかさめ)が降っている。
傘を叩く雨の音は聞こえないけれど、その透明なビニールの表面に浮かぶ水の玉は、
緩やかに、しかし確実に、その数を増やしてゆく。
そんな中、ぼくは沼名前神社の参道をぺたぺたと歩く。
石畳をたどり、二の鳥居をくぐる。
すると、随身門の手前で大勢の人たちが、何かの作業をしているのが目に付いた。
標柱(しめばしら)の根元には、軽トラックが2台停まっている。
参道の脇、旺然と繁る夏木の下に、木組みが窺える。
みんな、その木組みを取り囲んで、真剣にそれを仰ぎ見ている。
傘も差さずに、仰ぎ見ている。
何だろう?
ぼくは不思議に思って、近付いてみる。すると、
そこには巨大な松明(たいまつ)のようなものが、
2つ立て掛けられていた。

お手火奉製作業所の風景
公称・重さ200キロ、さあ実際は?
木組みの上では、ふたりの男の人が、その立て掛けられた巨大な
松明を紐で固定していた。
傘を差している人はいない。この程度の雨なんて、
誰も問題にしていないようだった。熱気に溢れていて、
作業する人たちの体からは 湯気が出ている。
ちょうどその時、反対側の参道脇に立つテントから、
さらにもうひとつ、巨大な松明が運び込まれようとしていた。
松明は10人がかりでえっちらと抱えられている。それから、
他の2本と同じように、木組みに立て掛けられる。
これだけ大きいと、立て掛けるだけでもひと苦労だ。
近くに看板を見つけた。そこには、
「お手火奉製作業所」
と書いてある。なるほど、ここで、あの有名な鞆の火祭り ・『お手火神事』の
準備をしているのだ。
ぼくは傘を閉じて、テントの中を覗いてみる。そこには、
木材や裁断機など、作業に関するさまざまな物が、所狭しと転がっている。
そこで、ぼくは橋本さんと出会う。
沼名前神社祭事運営委員会の橋本会長。
水色の作業着姿で、まさに陣頭指揮、といった感じだ。
ぼくがこのお祭の準備作業について教えてほしいとお願いすると、
橋本さんは快く頷いてくれる。
さっそくぼくは、テントの外の松明を眺めながら訊ねる。
「あれはどれくらい重たいんですか?
大勢でやっと運んでましたけど」
「200キロです」
と、橋本さんは答えて、それから、すぐに笑いながら付け加える。
「公称ですけど」
公称? じゃあ、もっと軽いのかな?
「実際量ったところ、235キロくらいありました」
「235キロ?」と、ぼくは驚く。
公称よりも重たいんだ。
「以前に、みんなでいっぺん量ってみようやって話になって、
で、量ったら200キロ超えとったんです。
きっかりはできんのでね。重うなったり、ちょっと軽うなったり、
太うなったり、いろいろ年によって違うんでね。
一応、重さ200キロ、長さ4メートルいうことにしています」
カンカンと杭を打つ甲高い音が、そこかしこで響いている。
その音を聞きながら、ぼくは独り言のように言う。
「これに火がついたら、どうなるんだろう?」
「そりゃあ、もう大変ですよ」
と、橋本さんは笑いながら答える。
「200キロを超えるような松明が燃えるんですからね」
うん、たしかに。それは、ほんとうに大事だ。

採火と輪番制
氏子青年たちの誇りと血の滾り
ぼくは橋本さんに連れられて、沼名前神社の石段を上る。
立派な随身門をくぐり、大石段を一段一段上っていく。
氏子たちは火のついた巨大な松明を担いで、この石段を上るのだ。
まったく、想像するだけで汗が滲んでくる。
石段を上りきり標柱をくぐると、本殿が目の前に現れる。
翡翠色の屋根と白い柱が、ぼくの目に鮮やかに映ずる。
本殿前には、木材を組み合わせて作られた、
体操競技の平均台みたいなものが置かれていた。
今まさに設置作業が進められているようすで、その木組みの周りでは、
幾人かの人たちが杭を打ったり、麻縄を巻いたりしている。
「これは何です?」
とぼくは聞く。
「祭当日に、お手火をここまで担いでくるわけですけど、
最後に3つここに立て掛けるんです」
なるほど、ここが担ぎ手にとってのゴールなんだ。
「ここまで担いでくるのに、大体どれくらいの時間が
掛かるものなんですか?」
「うん。3時間はたっぷり掛かるかな」
と、橋本さんは答える。
「20時からご祈祷して、神前手火(しんぜんてび)いう、
ちょっと小さめの松明があるんですけど、神社の本殿の中で採火、
ようするに火を頂く。そして、白装束の各町の代表が、火を移した
神前手火を担って降りてくる、と」
ぼくは、その情景を想像する。白装束姿の人が神火を抱いて、
この石段を下る。なんとも幽遠の趣がする。
橋本さんは続ける。
「で、その神前手火から、下の3つの大手火に火を移すんです」
なるほど、下の大きい松明は、「大手火」というのか。
「大手火は『先の隊』、『中の隊』、 そして『後の隊』と3体あるんですけど、
順番に『先の隊』から火を移していきます。
旧鞆町構成7町で当番を回していますが、その内、元町と江の浦町だけは、
毎年この『先の隊』を担ぐことになっています。
『中の隊』と『後の隊』は、それぞれ3町ずつが順々に当番を廻してね、
今年の『中の隊』は西町。で、『後の隊』は石井町。中と後の当番町は
3年に1回、順番が回ってくるいうことです」
ぼくは、当番町の氏子青年たちの誇りと血の滾りを思った。
祭当日の熱量たるや、一体どれほどのものだろう?
その時、本殿の後ろに鬱蒼と広がる木々が、
ざわっとひとつ、風に揺れた。

三週間、夏の祭典
神様の通り道を清める、祓いのお手火
ぴーひょろろ~とトンビが盛んに鳴いている。沼名前神社の境内にあって、
トンビも、自然も、作業に当たる人たちも、みんなとても元気だ。
橋本さんは本殿前の木組みを眺めながら、話を続ける。
「3体の大手火がここに揃ったら、それらをもう度担いで、それぞれの
当番町へ持って帰るんです。それで、翌日に神輿が出る経路を、
あらかじめ清めていくわけです」
火は浄化の力があると昔から信じられてますから、と橋本さんは付け加える。
ぼくは驚いて訊ねる。
「せっかくここまで運んできたこの大きなお手火を、
また担いで練り歩くんですか?」
橋本さんは、はははと笑って答える。
「3時間も燃えていれば、大分小さくなりますから」
あ、なるほど。
橋本さんは続ける。
「それで、お手火を各当番町に納めて、とりあえず一区切り。
で、次の日に今度は、渡御祭(とぎょさい)いうて、神輿が
出るんですよ。祇園の神様が神輿に乗って、町に降りてこられる」
「え?お手火神事って、一日だけで完結するお祭じゃないんですか?」
「お手火神事いうのは、祇園宮の祭神、スサノオノミコトが神輿で町を
巡られる一連の祭の中の、ひとつの祓いの儀式という位置づけなんです」
うん? 露払いということかな。
「まず、お手火神事があって、その翌日に渡御祭。
神様が神輿に乗って巡られる。で、お旅所で神輿廻して、そうして
神様は一週間そこでお休みになる、と。そして、翌週の日曜日に、
今度は祇園宮に還って来られる。還御祭(かんぎょさい)いうてね。
そうして、それからまた一週間後の日曜日に神能祭いう、神様に
能を奉納する祭事がある。それで一連の祭りが終わり」
そう言って、橋本さんは話を整理してくれた。
ようするに、三週間の長きに渡るお祭り、ということだ。
ほんとうに、地域のエネルギーが、惜しみなく注がれているんだ。
だからこそ、事前の準備から、これだけの人が汗を流すのだね。
なっとく。

大切なのは、火加減、それに水加減
火祭りの、隠れたる繊細微妙な伝来の妙技
ぼくはずっと下に伸びる大石段に目をやりながら、橋本さんに訊ねる。
「当日は、この石段も見物人で溢れるわけですよね?お手火の近くで見ている
人なんて、危なくないんですか?」
「お手火だって、右行ったり左行ったりしながら進むんで、
それなりにね。この時期だから、よく雨も降りますし、滑ったりもね。
でも、そのために警護もつきますから」
「じゃあ、安心ですね」
ぼくがそう言うと、
「でもね」
と橋本さんは切り返す。
「根っこを背負う者、『一番』って我々は呼んでるんですけどね、
その『一番』なんかは、落ちてきますからね、火が、ぱちぱちと。
で、どうしても次の朝なんて火脹れがね」
やっぱり過酷には違いないんだ。
「その『一番』が〝いちばん〟きつい場所ってことなんですね」
ぼくがそう言うと、橋本さんは笑いながら
「そうそう」
と答える。
「ちなみに、お手火には油って塗るんですか?」
「いえ、塗りません。見てもらったらわかる思いますから、
ちょっと移動しましょうか」
そう言って、橋本さんはぼくを先導する。
ぼくたちは石段を下っていって、能舞台のすぐ下にある吹き抜けの小屋に至る。
そこには、多くの木材が保管されている。材木置き場のようだった。
橋本さんはひとつの丸太に手を添えて言う。
「お手火の木の素材は主に松なんですけど、古い松は松脂がよく染みてる。
そういう木はしぶとく、じわじわと燃えてくれるんですよ」
いい火を作るためには、材木から。そのこだわりは、すごい。
「でも、粘り強く燃える松明を作るってことは、担ぎ手としては、
ずっと熱さと付き合うってことで、やっぱり大変なんでしょうね」
橋本さんは、うんと頷きながら答える。
「だからみんな、ドンゴロスいうね、あのコーヒー豆入れるような
麻袋いうんかな、そんなのを水に濡らして火を防いだり、
水をそのまま頭からかぶったり、しょっちゅうするわけなんです。
で、火にも水をやってね」
え?火に水をやる?そんなことしたら消えてしまうのではないだろうか。
「火の強さをうまいこと調節するんですよ。担ぎ手を守るのもそうだけど、ずっと火が
強いままで上がって来ちゃうと、石段を上がりきった時には、全部炭になってしまう。
だから水を足したりして、加減するわけです」
はあ、なるほど。
「でも、その加減が難しそうですね」
「そうそう。素人がなまじ水かけたりすると、消えてしまうんよ。
でも、消えてしまういうても、階段を蛇行するなり、お手火を揺らして木の間に
風を入れるなりすると、また火がつく場合もあったりね」
あの血気盛んに映る火祭りの中にも、こんな繊細微妙な技があるんだ。
一朝一夕では身に付かない伝来の妙技。感服しました。
「火種っていうのは、案外しぶといものなんですね」
ぼくがそう言うと、橋本さんは少し首を横に振りながら答える。
「ところがね、それでも、去年かおととしは、
つかんかった。 その時は2体目が消えたんですけどね、
結局、3体目から もらい火してな。下まで戻って、
つけ直すいうことはできんから」
うん、ほんとうに難しいものなんだね。

松と親しく
匂いでね、わかるんですよ
ぼくは、保管してある松の丸太を眺めながら、橋本さんに聞く。
「ここに置いてある松って、鞆で採れたものなんですか」
「いえいえ、他の色んなところにお願いしてもらってきたものです。
あと、鞆の古民家を倒した時に出た廃材とかね。なかなか最近いい材料が少なくて、
じっくり長く燃えるのが足りないんです。 ぱっと燃えてすぐに灰になるのばかりで」
うん、材木調達の苦労は多いのだろうと思う。
「だから、こうやって、もらってきた松を寝かして、ある程度乾かすわけです」
橋本さんはそう言って、パンパンとひとつの丸太を優しく叩く。
「これなんか、福山八幡宮で松を伐ったものをもらってきてね。
こうして、来年以降のために保管しているんです」
そして、橋本さんは手刀を切るような身振りをして、続ける。
「手作業である程度の大きさと長さに割って、それから、
先っぽをとがらせてまとめていくんですけど、その作業がすごい手間が掛かる。
5月の中頃から始めて、平日、月曜から金曜まで、朝、
みんなでここに集まって作業して。で、出来上がったのが6月の末ですからね」
まったく、気の遠くなるような話だ。
「でもね」
と、橋本さんは言う。
「こうやってずっと松に触れてるとね、いい松かどうかって、
だんだんわかってくるんです」
「それは、どんなところで?」
「削ってると、匂いで。いい匂いがね、するんですよ、脂が染みてるやつは」
そうやって松と親しくなることで、あの大きなお手火に「想い」が
こもっていくんだ。ぼくも試しに、すーっと鼻腔を拡げてみた。
うん、ぼくにはやっぱり、よくわからない。
「ちなみに」
と、ぼくは気を取り直して、橋本さんに訊ねる。
「お手火のあの組み方は代々伝わっているものなんですか?」
「ええ、継承していくものですね。あの縄の結び方も決まったやり方で
結んでましてね。昆布みたいな、あれ、『男結び』いうてね。
鞆独特というわけでもないんでしょうが、まあ、継承されているものです」
「それは、何とも勇壮な名前ですね」
ぼくがそう言って感心していると、橋本さんは、
からりと笑いながらこう答える。
「わたし、結べませんけどね」
あはは。それはそれで、豪放だ。

大手火囲む、小手火の海
小手火作りにこめる、「想い」
橋本さんは、テントの奥にある平屋の作業場に、ぼくを案内してくれた。
2、30畳はあるだろうか、かなりの広さの畳部屋にブルーシートが敷かれている。
その上に、作業道具や細めの木材、縄などが置かれている。
扇風機や蚊取り線香もある。
橋本さんは両手を野球のバットくらいの幅に広げて言う。
「ここで、このくらいのね、お手火の小さいやつをたくさん作ります。
見物客がお手火から採火して家に持ち帰り清めるための、小さな松明ね」
「え、小さな松明?そんなものも作るんですか?」
「うん。小さなお手火だから、小手火いうてね、これは
百五十本くらいは用意する。けっこう手間なんですよ、これがね」
「そうでしょうね。百五十本も作るんですものね。
でも、家に持って帰ってお清めできるって、いいですよね。
とてもありがたい感じがする。ぼくも持って帰りたいな。
見物客、取り合いなんじゃないですか」
橋本さんは、いやあと首を振る。
「今は持ち帰る人がずいぶん少なくなりました。むかしは、
見物客のほとんどの人がこれを持って、大手火の周りを取り囲んでね。
この小手火が石段を埋め尽くすように燃えとって。
それで、一面炎で揺れとる、みたいにね。
今は、ほとんど 誰も持たんから、大手火だけがよじ登っとる
格好になってますけど」
そして、橋本さんは懐かしそうに言う。
「むかしは、境内のあちこちにね、小さい炎が揺らいで、
まるで火の海みたいじゃったんだけどね」
ぼくも、その光景を思い浮かべてみた。
橋本さんの見てきた景色は、ぼくには残念ながら想像することしかできない。
実際は、一体、どんな景色だったんだろう。
往時の火祭りのにぎわい。
大手火囲む、小手火の海。

当番町の誇り、伝統の重み
伝統の炎の色を目に焼き付けたい、
ぼくはそう思った
「むかしはすごいにぎわいだったんですね」
ぼくがそう聞くと、橋本さんは、うんと少し寂しそうに頷く。
「そうなあ、人口多かった時はね。当番町で担ぐわけですけど、今じゃあ、
その町の若い者を総動員しないと数が賄えない。
年寄りが担ぐいうても、それはなかなか厳しいんです。
町内だけで担げる人が足らんわけですよ」
「そういう場合は、どうするんですか」
と、ぼくは訊く。
「外から人を頼んだりね。例えば、福山のほうから
大学生ちょっと手伝うてくれへん、とか頼むんです。
親戚だとかが鞆の近くにいる人は、
呼んで手伝ってもらうなんてこともあるけれど、
それでも追いつかん時は、もう、よそから頼んでね」
ぼくは言う。
「でも、よそから来た人は感動するでしょうね。
こんな祭りに参加できて」
「でも、なかなか難しい事情もあるんです」
何だろう?橋本さんは続ける。
「町によっては、すんなりと担がせてくれん町もあるんですよ。
それぞれの領分があるからね。けっして1番目のお手火を担ぐ者が、
2番目、3番目のお手火を触っちゃいかんとかね。
ちょっと間違って触っちゃったっていうても、
えらい問題になるんです。もめてね。担ぐ当番町が責任と誇りを
持ってやるいうのがルールなんでね」
ぼくは、その気概に触れて、鞆の人の伝統への「想い」の深さを、
改めて思い知った。 人が足りない、だから外の人、
助けておくれ、という話ではないのだ。
ぼくは、この火祭りに懸ける橋本さんたちの
「物語り」に触れて、伝統の重さ、というものを、
少しではあるけれど、感じ取ることができたような気がした。
祭当日はもう目前に迫っている。伝統の炎の色を、しっかりと
この目に焼き付けたい。
ぼくは強く、そう思った。




