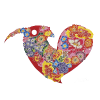
小豆島食品 久留島克彦さん

醤の町で生まれた佃煮
ご先祖様は島の塩
山と海に囲まれた、自然豊かな小豆島町。
町を歩くと、鮮やかな朱色の旗が目についた。
内海の潮風にたなびく旗には、
白抜きで「醤」の文字。
醤油蔵や、その醤油を使っている佃煮屋が軒を連ねる
この一帯が、「醤(ひしお)の郷」である。
「醤」の旗を目印に歩いて行くと、
醤油工場や佃煮工場を散策できる。
醤とは、塩をまぜて発酵させた調味料のこと。
小豆島では弥生時代から、塩作りが行われていた。
そこに、肥前や肥後から大豆や小麦が運ばれてくる。
良質な島塩と、海運がもたらした穀類は、
発酵と熟成に適した瀬戸内気候の中で、
ゆっくり育まれ醤油へと変わっていく。
塩から醤が生まれ、醤から醤油が生まれ、
醤油から佃煮が生まれた。 古代から江戸時代、
現代へと食の改変が続いている。
「醤」の旗を見ながら、時の流れに思いを
馳せていると、 どこからともなく、
お醤油の良い香りが漂ってきた。

小豆島食品、自慢の逸品
いままで食べたことのない佃煮
「お昼ごはん、もう食べましたか?」
お昼すぎ。醤油の良い香りに誘われて立ち寄った、
小豆島食品。 明治時代に建てられた醤油工場で、
有形文化財にも指定されている風情ある焼杉の
壁の建物に、事務所と佃煮工場を構えている。
社長の久留島克彦さんが、にっこり微笑みながら
私たちに声をかけてくれた。
小豆島食品は、克彦さんの祖父の代に創業を開始した佃煮屋。
克彦さんは小豆島で生まれ育ち、4年間だけ島外の大学に
通った後、22歳で島に戻り、店を継ぐことになる。
「明治の建物で佃煮を作っているのは、
全国でもうちだけじゃないかな」
小豆島食品では、工場見学も行っている。
ご飯を持参し、タイミングがよければできたての
佃煮を頂ける、かもしれない。
「今日は特別ね」
あいにく手ぶらだったが、私たちのお腹の鳴る音が
あまりにも大きかったのか、克彦さんは笑いながら
ご飯を用意してくれた。
香川県の親鳥の胸肉だけを使った「鳥そぼろの佃煮」、
瀬戸内の小エビを使った「小エビのしぐれ煮」、
「ちりめん山椒」、人気ベスト3が目の前の
テーブルに並んだ。
いままでに食べた佃煮では味わったことのない、
素材の風味とやわらかな食感。 穏やかな瀬戸内の
恵みを凝縮したかのような、やさしい香り。
目からウロコの美味しさに箸がとまらず、
頂戴した佃煮でご飯を全部平らげてしまった。
満足そうな表情を見せて克彦さんは言う。
「これより良い佃煮を探そうと思ったって、
ほとんどないと思いますよ」
自信をもって作るからこそ、
みなさんに安心して食べてもらえると、
克彦さんは言う。

流通の変革と原点回帰
至上の佃煮をめざす
工場には、いくつもの大きな釜がある。
かつて、この大釜では、いまよりもずっと
大量の佃煮を炊いていたという。
それでも作った分だけ、
どんどん佃煮が売れた時代──。
しかし、世の流れに伴い流通の改革が進むと、
小豆島の佃煮産業にも変化が訪れる。
各地にコンビニやスーパーが立ち並び、便利になった。
と同時に流通のルートが変わり、全国展開するような
店舗は大きな商社から仕入れるようになった。
小豆島食品のような小さな問屋を
必要とする小売店が、少なくなってしまったのだ。
「大型チェーンの台頭で、日本全国どこへ行っても
一定以上の品質のものが手に入るようにはなりました」
しかしこのままでは、小豆島という小さな島の、
小さな佃煮問屋は経営を続けられなくなってしまう。
うちならではの、個性きわだった商品を作れないだろうか。
このとき克彦さんが出した決断。
それは、「原点に帰ること」だった。
その“原点”とは、志半ばにして断念した
「無添加の佃煮」を作ること。
「無添加で、これ以上のものはないといえる最高の佃煮を作ろう」
店を守るため、克彦さんは決意を固める。
過去の自分が、「もう一度やってみよう」と
エールを送っている。

こだわりの素材選び
無添加だけでは続かない
今から30年ほど前、世間に無添加ブームが起こった。
小豆島食品も流れに乗るべく、無添加の佃煮に
挑戦したという。
「無添加は無添加なんですが…どうも味がついていかない」
いくら体に良いといっても、
味に満足できなければ人は買ってくれない。
無添加の佃煮に関しては苦い経験を持つ
克彦さんだったが、 時代の流れと過去の自分に
背中を押され、至上の無添加佃煮作りが始まった。
以前のレシピを元に、味を調合し、毎日毎日、
試行錯誤しながら佃煮を作り続けた。
30年前とは明らかに違うことがあった。
それは、素材への並々ならぬこだわり。
「昆布ひとつとっても、採れた浜や等級に
よって細かく分かれているんですわ」
佃煮の出汁として使われている利尻昆布。
利尻産とひと口に言っても、広い浜のどこで
採れたものかによって味が変わってくるという。
克彦さんは自らの足で北海道に赴き、
昆布問屋から各浜で採れる昆布の特徴を聞き出す。
これは、と思う昆布を見つけたら、仕入れて試作品を作る。
「昆布だけで、何十種類と炊いています」
同様に、醤油、砂糖、鰹ダシも吟味厳選し、
同じ小豆島のヤマロク醤油、鹿児島県喜界島の粗糖、
枕崎産の鰹節を選んでいく。
しかし、無添加と美味しさを両立するには、
さぞ苦心したのではないだろうか。
克彦さんは、「そんなことはないのです」と笑う。
「30年前の無添加のノウハウに、
品質レベルをプラスすれば良いだけ」と、
さも明快に言い切った。
ただひたすら、日本中の良質な素材を探し歩き、
試作品を作り続けるのみ。

本当の無添加、本物の美味しさ
そして、職人の手仕事
「良い物を作ろうとしたら、
良い原料を探して歩かないといけない」
人に任せず、自分で調べ歩き、手にした厳選素材。
それを直火にかけながら、機械ではなく自らの
手でじっくり撹拌する。
「昆布にしても、一定の厚みじゃないのです」
薄いところがあったり、厚いところがあったり。
採られた年によっても昆布の厚さは変わってくるという。
素材を見て炊き加減を変え、手の感覚、見た目を
確認しながら砂糖の投入時間を変えていく。
機械では、この微調整は不可能だ。量産ではなく、
素材の味を大切に、特徴を活かしながら丁寧に作る。
「良い物を作ろう」
克彦さんの思いが通じ、小豆島を訪れる人や、
各地で開催される物産展などで小豆島食品の佃煮は
評価されていった。
今は全国で販売され、こだわりの逸品として
贈答用にも喜ばれている。
「うちの佃煮は、富士山でいうと七合目と、
それから一番上のところに大きく分けられます」
業務用やお弁当用として大量生産される佃煮ではなく、
「準高級品と最高級品」という位置付けだ。
素材選びと同様、誰に訴求したいかまで的を絞った。
職人としてのこだわりと、経営者としての判断力、
両方の素質を克彦さんは兼ね備えている。
歴史ある醤の町には、美味しい佃煮と、本物を見極めることで
会社を成長させてきた克彦さんという人の物語りがあった。
島の恵みと、島の人たちに感謝の気持ちを込めて伝えたい。
「ごちそうさまでした」




