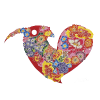
WEBデザイナー 牧浦嘉徳さん
大阪で熱心に仕事をしていたが、遊びに来た小豆島に魅せられ、
2013年8月、家族と共に小豆島に移り住んだ。
引っ越して生活が変化したというが、
新しい暮らしで失い、そして手に入れたものとは…?

豊かな自然に囲まれた
理想の島ライフがここにある
仕事場から続くウッドデッキに出ると、
眼下には瀬戸内の海が広がっていた。
波の音に耳を澄ませると、
背後の里山から優しい鳥の鳴き声も聞こえてくる。
海と山、自然に囲まれた素晴らしいロケーション。
島ライフを送りたいと思う人が想像する、理想的な住み家がここにある。
小豆島でWEBデザイナーとして活動している
牧浦嘉徳さんの自宅兼仕事場だ。
鳥の声を聞きながら、美しい海を眺めていると、
思わず「こんなところで暮らせたらなぁ」
という言葉が口をついて出た。
「実はね。この家は、
当初計画していた家賃の予算をオーバーしていたんですよ」
愛猫ピロこと、ピロシキの背中を撫でながら、
牧浦さんは私のほうを見てニッコリ微笑んだ。
この家を借りると決めたことで、
仕事のやり方を変えざるを得なかったと言うが、
今になって思えばそれが良い方向に働いたという。
「小豆島への移住を決めたとき、そのとき勤めていた会社を辞めて、
フリーの立場で手伝えることがあったら、
手伝わせてほしいと会社にお願いしていたんですよ。
でも、会社を離れて仕事がゼロになっちゃうのは嫌だし、
何かいい方法はないかと考えていました」
そんな時に見つけたのがこの家だという。
不思議なことに、家を見つけた直後から話がいい方向へ転んだ。
会社を退職するのではなく、
小豆島での在宅勤務という形で、月に何度か大阪の会社に出向く。
そんな条件で勤務先と話がついたのだ。
「それなら、なんとかやって行けるぞ。
ここの家に住めるぞって落ち着いたんです。
この家を借りることができたから、
より良くなったというのが絶対にあると思う」

今の環境を変えたい──
思い出から探る変化の手段
牧浦さんが家族と共に小豆島で移住をはじめたのは、
2013年夏のこと。
それまでは、兵庫県西宮に在住し、
職場であるデザイン事務所は大阪にあった。
「40分くらい電車に乗って、大阪に通っていたんですよ。
帰りも遅くて、だいたい終電に乗る。
終電を乗り過ごすこともよくありました」
結婚して家庭を持ったけれど、
家にいる時間は少なく、家族と触れ合うこともままならない。
朝、電車に乗って通勤し、事務所の中で一日作業をして夜中に帰宅する。
毎日、その繰り返し。
無自覚ではあるが着実にストレスが溜まっていき、
些細なことで苛立ちを感じるようになっていく。
「通勤の電車を待っているとき、後から来たのに列の前に入ったり、
車内で足を投げ出して座席に座っていたりする人を見ると
イライラしちゃってね。
電話しているとか、音漏れしているとか、
いろいろなことが気になって」
環境を変えたい──。
その方法を探していたとき、牧浦さんの脳裏に、
亡くなった父親の姿が浮かんだ。
「思い出の糸口を探していたとき、
うちの親父が小豆島にいる人のことを話していたのを思い出したんです。
『妖怪の絵を描いている変わった子がいるんだよ、
お前と年も近いし、機会があったら会ってみたらええなぁ』
って言われてたんです」

父親が見た小豆島
景色、人、文化を共有したい
父親の言葉に導かれるように、牧浦さんは観光目的で小豆島を訪れた。
「本当に思いつきです。週末ちょっと小豆島に行こうか?
みたいな軽いノリで遊びに来た」
ただ、心のどこかで、
「親父とつながりのあった誰かに会えたらいいな」
という思いがあった。
牧浦さんの父親の徳昭さんは、京都で呉服屋を営んでいたが、
晩年プロデューサーとして活動し、
多くのクリエーターを世に送り出した人だ。
そして、小豆島にも何度か足を運んでいた。
敬愛する父親が見ていた景色を共有できたら、
という思いで小豆島を訪れた牧浦さん。
父親が言っていた「妖怪の絵を描いている変わった子」、
小豆島を拠点に妖怪をモチーフにした作品を制作している
柳生忠平さんその人とも会えた。
島を観光する中で、
牧浦さんの心に小豆島の自然や人、文化、
暮らしがスッと入ってきていた。
「もともとスローライフとか、そんなんじゃないですけれど、
のんびりした生活っていうのに憧れていた。
それで、ちょっと頭の中で考え始めて……。
小豆島だったら、神戸まで船で3時間。
不便といってもたかが知れているし。なんとなく、住めたらいいなと」
翌月、牧浦さんは再び小豆島を訪れる。
島を巡りながら、移住への気持ちがしっかりと固まっていく。
「なんのあてもないですよ。
でも仕事柄ね、
パソコンとネット環境さえあればどこでもできるだろうし。
自分の中で、いろんな仕事とか、できる自信はあった。
そしたら、移住してもいいじゃんって。
それで、小豆島から家に帰ってきて、
妻に『移住せん?』と話を持ちかけたんですよ」

必然だったような移住
父が紡いだ縁に導かれる
突然、移住の話を切り出され、
奥さんはさぞ驚いたのではないだろうか。
土地勘もなく知り合いもいない、
新しい場所での暮らしに不安を覚えてもおかしくない。
「意外にあっさり。『いいんちゃう』みたいな感じでしたよ。
『仕事があるなら』ってね」
移住が本決まりになり、住居探しに何度か小豆島を訪れ、
今の物件に巡り合い、移住の具体的な段取りも決まった。
「縁ですよね。必然みたいな感じ、
僕は導かれているみたいな気持ちだった」
「WEBデザイナーの仕事を始めたのも、親父がきっかけなんですよ」
二十代の頃、牧浦さんは仕事をせずに家にいたときがあったという。
何かしたいと漠然と考えているとき、
父親が人からパソコンをもらってきた。
その中に、デザイン用ソフトが入っていた。
牧浦さんはそのソフトを活用し、遊びでホームページを作りはじめる。
「周りにいる友だちしか
見ないようなホームページを作って更新していたら、
今の勤務先の代表との縁がつながり、
『仕事手伝ってくれへん?』という話になって、
最初はフリーランスでWEBデザイナーとしての仕事を始めたんです」
職種によっては在宅で仕事をすることは難しいと思うが、
牧浦さんの場合はパソコンさえあればどこでも仕事ができると言う。
働き方としては、
まるで、小豆島に移住することを見越していたかのような好条件だった。

シンプルに生きよう!
消費サイクルからの脱出
「地方に移住してネックとなるのが、打ち合わせと、
安定的に仕事が入ってくるかどうかだと思うんですよ。
これさえクリアできたら、
こんなにいい環境はないと思っています」
月に数回、仕事の打ち合わせで大阪に足を運ぶときは、
ジャンボフェリーの始発に乗り、その日の深夜便で帰ってくる。
「船の中で泊まるような感じですね。
一刻も早く島に帰りたいから、大阪には泊まらない」
都会にいると、「何かしないといけない」
という感覚になると牧浦さんは言う。
「例えば、平日はずっと仕事。
だから週末になったら何かしないといけないと思ってしまう。
家族とどこかに行かないととか、買い物行かないととかね。
常に何かしっぱなしなんですよ」
「何かしないといけない」という焦りが、島にいると、
何もせずボーっとしていてもいいという感覚になった。
「シンプルに生きよう。必要最低限のもので、充分満足」
そう思った。
「街にいると消費させられている感覚になる。
いろいろ物があって、何でもすぐに買えてしまうばかりにね」
何かを求めなければいけない感覚。
世の中のサイクルの中で、
常に消費させられ、常に疲弊している感覚。
小豆島に移住後、そんな感覚は抱かなくなった。

島から街を見て気づいた
心が求めていた価値観
「僕ね、小豆島に来てから丸くなったらしいんですよ。
全体を捉えた見方というのができるようになった」
それは、島から街を見る感覚に似ているという。
島と街の違いを冷静に考えられるような、
客観的な見方が養われた、と牧浦さん。
「今までは何に対しても前のめりだったのが、
ちょっと余裕ができたと思うんですよ。
それで、お客様には、
これまで以上に客観的な視点から提案できるようになった」
技術的なことは変わらないけれど、
感性が豊かになったという点で、
WEBデザイナーとしてのスキルが上がった気がするという。
小豆島にいると、自分の中に余裕が生まれ、
お客様のことをもっと知ろうという気持ちになり、
コミュニケーションを図る機会が増えた。
相手の求めていることが、
具体的にイメージできるようになってきたのだ。
「仕事をしていて、楽しいですしね」
ニコニコと微笑む牧浦さんの隣で、奥さんも
「島に来て、トゲがなくなったかもしれない」
と言って、笑みを浮かべた。
牧浦さんがいう。
「もともと望んでいた価値観に、
スッとおさまったという感じです」
ずっと、違和感を抱いて生きてきたが、
小豆島に来てそれが一切無くなったそうだ。
会社や仕事を中心にした生活を
当然のように大切に思っていたけれど、
一歩引いて見ると逆に手放してもいいと気づかされるものある。
そんなものを、もしかしたら自分も抱えているかもしれない──。
牧浦さんの話を聞いている中で、ふとそんな思いが浮かぶ。
目の前に広がる小豆島の自然が、
「そうだよ〜」と言っているような気がした。




